Home
Home |
||
| 1/29夜 とんがりやまさんの場合 | ||
|
1/29夜 Jagrさん めいすけさん 國京さん M. さん ERINさん Yukiさん とんがりやまさん |
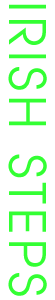 |
まず最初にお断りしておきたいのですが、LOTDの場合どうしても作品論をやりたく なってしまうのですね。「公演レポート」の趣旨からははずれるし、以下の私の批判的感想もさほど目新しいものとは思えないので、読者の方々、この項は飛ばしていただいて結構です。…だったら投稿するなって?いや、ごもっとも。 CD解説に大島豊氏も書いておられるように、LOTDを語るにはまず「リヴァーダンス」から始めねばなるまい。初代プリンシパル、マイケル・フラットレーがリヴァーダンスの制作側と対立したからこそ、自ら新しいショーを立ち上げるに至ったわけだが、LOTDは結局リヴァーダンスの呪縛から逃れられなかったのかもしれないな、というのが、来日公演を観た第一印象であった。 もちろん新機軸はいくつもある。特筆すべきはやはりアイリッシュ・ダンスでダーク・サイドを描いた点で、こればかりはまるで<文部省推薦・アイルランド政府観光局御用達>のようなリヴァーダンスには絶対できなかった表現であろう。気持ち悪いくらい揃いすぎる集団ステップ・ダンスに、ナチス的軍隊のイメージを重ね合わせる部分など、マイケルの天才が遺憾なく発揮されていると思う。あるいは妖婦モリガンに代表される性的イメージ(アイルランドにおけるフェミニズムの問題は大野光子『女性たちのアイルランド』平凡社選書/1998年、に詳しい)。これはしかし、一部のアイルランド人からは猛反感を買いかねないイメージでもあり、フラットレーはやっぱりアメリカ人なんだな、と思う。おそらく彼がリヴァーダンスを抜けざるを得なかったのは、こういうメンタルな部分にもあったのではないか。 …以上のような<新味>を打ち出し、さらにはリヴァーダンスよりもよりダンスにこだわったステージングにもかかわらず、フラットレーがかの偉大なる先駆の呪縛から逃れ得なかった点はなにか。そのひとつに音楽とバック・ミュージシャンの扱い方を挙げたい。 まず、この作品においてはミュージシャンが前面に登場する必然性は、さほどない。女神エリンのみが<歌=言葉を持っている>という設定はひとまず良いとしても(しかしなんで女神の開口一番が『シューリ・ルゥ Suil a Run』なんだろう?しかも、日本版ヴィデオの字幕の歌詞をかなり意訳してあるのは意図的なんだろうか)、2人のフィドラー、そして他のバック・ミュージシャンがステージに下りてきて演奏する場面ははたして必要だったのかどうか(第二部、The Lament と Siamsa の間。ヴィデオ版にはない)。しかも、中途半端なことにドラムスやキーボード奏者は下りてこないのだ。せめてバウロンくらい持たせたらどうなんだ?と思ったのは私だけではあるまい。この場面はリヴァーダンスの、特にニューヨーク公演版を意識しすぎているのではないか。 なにより物語の一番のクライマックス、闇の神に捕らえられて以降の対決から勝利までの部分は、音楽はオーケストラ。それまで顔見せまでしていたボタン・アコやフィドルなど伝統楽器プレーヤーは、最大のハイライトで完全に用無し状態なわけで、これならはじめからテープを流しておいても構わないことになる。音楽を担当したロナン・ハーディマンの最大の弱点だろう。実際、こと音楽のみを取り出してみるとこの作曲家の凡庸ぶりがよくわかる。ま、音楽とダンスが対等に渡り合うリヴァーダンスと比べるのは、ちと酷かもしれないのだが。 演出面では、特に音響が気になった。終演後鼓膜が痛くなったほどで、あそこまで高音を強調しなくても良いのにと思う。掲示板では<足パク>疑惑が話題になっていたようだが、マイクでの増幅であれ後からタップ音をかぶせたものであれ、要は観客に違和感を抱かせなければよいだけの話であり、不自然さを露呈してしまったのはミキサーの責任であろう。現代の大規模公演では、なにかを強調するために多かれ少なかれテクノロジーの力を借りる必要があるのだし、そのこと自体を責める気はさらさらないのだが、どうせやるなら上手に騙して欲しい。引っ越し公演ならではの問題もあるとは思うが、会場でのスピーカーの配置を含め、音響スタッフがやるべき事はまだまだあるはずだ。 笑ったのは、手を振り下ろすときに出る「ヒュッ」という効果音。まあストーリィ自体所詮アメリカン・コミックスなのでそういう演出も悪くはないんだが、どうもハリウッド映画の見すぎじゃないのか、みんな。そんな音響のせいなのかどうか、すぐ目の前で演じられているのもかかわらず、なんだかステージがとても遠いように感じられた。聞こえてくる音と目で見るものの間に、とても距離がある。ステージと客席の一体感が出にくかったのは、ここらあたりにも原因があるのではないか。 肝心のダンスは、さすがと言うべきもので、なんだかんだいっても、とにかくナマで観られたのは幸せだった。ただ、この作品ではどうしてもフラットレーのコレオグラフが話題の中心になるのは避けられないのだが、彼が振り付けていない(だろう)ダンス、特に第二部の Siamsa に見られる現代的ケーリー・ダンスの楽しさにはもっと注目していい。曲調とリズムが次々に変化していく、かなり複雑で難しいダンスなのだが、このフォーメーションの複雑さは現在の競技会用ケーリー・ダンスに共通のものだから、やろうと思えば基本ステップ(ケーリー・ダンスの場合、殆ど1種類しかない)をマスターした中学生でもできる筈だ。それよりも、ともすればハード・シューを使うモダン・ステップ一辺倒に見られがちなこの作品の中に、アイリッシュ・ダンスのもう一つの顔を見事に生かした名ナンバーを配した事をこそ評価すべきだろう。しかも、構成がヴィデオ版より格段に良くなっているのが嬉しい。 最後に、出演者について。主役がいちばん線が細かったのはしょうがないとして、フラットレーとおよそ正反対であろう資質の持ち主に、フラットレーと同じポーズ/仕草をさせるのはいかがなものか。天才によくあるように、フラットレーは「自分ができるものは他人にもできるはず」と思いこんでいるふしがあるのではないか。あるいはここはひとつ、キャラクター的にもっと「白馬の王子様」タイプでも良かったと思うのだが。フィギュア・スケーターで言うとアレクセイ・ウルマノフとかイリヤ・クーリック、なんてね。 また、出演者の名前を一切出さない方針もちょっと不気味だ。これも、主演クラスが次々にスターになっていったリヴァーダンスの逆を行ったつもりなんだろうか? …などと、ついリヴァーダンスと比較してしまう私のような観客こそが、あれの呪縛から逃れていない最たるものなのだろうな、きっと。 Lord of the Dance 2000トップへ |
|
|
[Home] [Irish Steps] [Tokyo Swing] [Beyond] あなたも自分なりの視点で書いてみては? air@myself.com |
|||